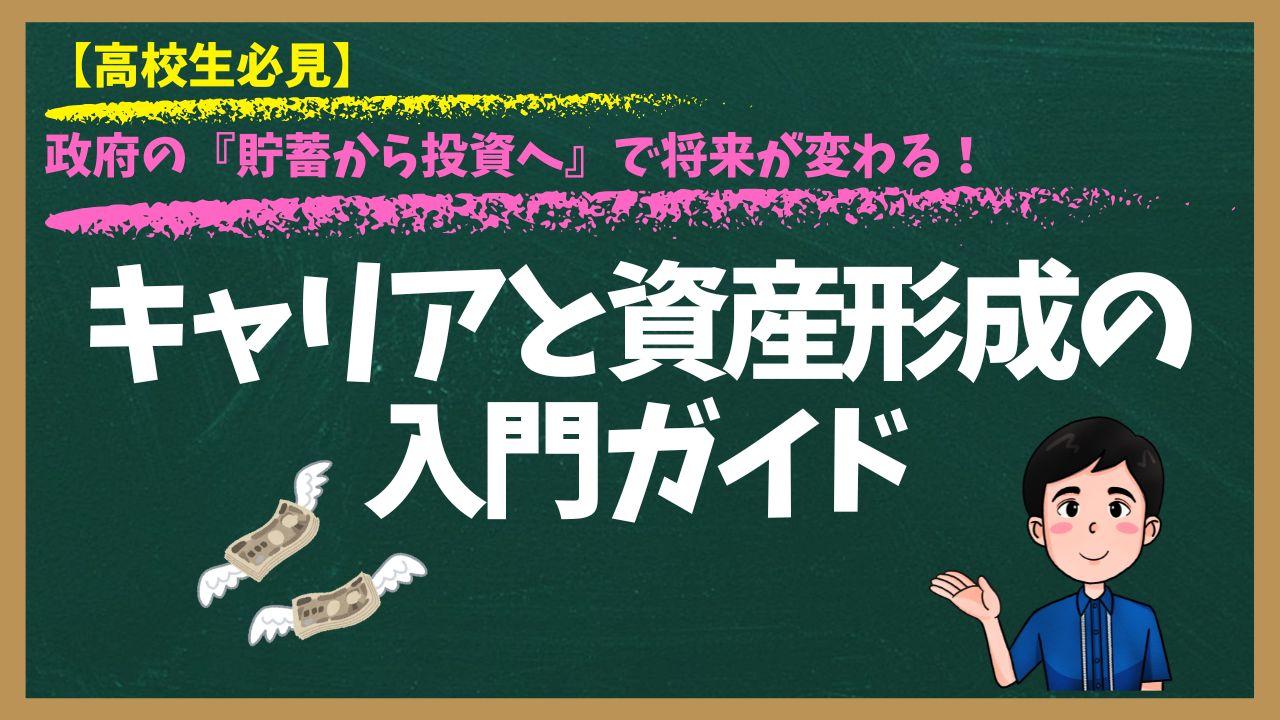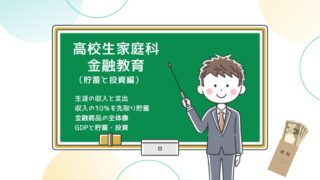【記事全体を貫くメッセージ】
政府の『貯蓄から投資へ』は、お金を増やすための社会の新しいルール。将来の給料だけでなく、あなたのキャリア選択が、資産形成の舞台を決める。
『貯蓄から投資へ』を支える賃上げと投資の好循環
政府は「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」において、2029年度までの5年間で実質賃金を年1%程度上昇させることを新たな「ノルム」として定着させると明記しています。これは、「賃上げこそが成長戦略の要」という方針に基づき、企業の設備投資やイノベーション推進と一体で官民連携で積極的に推進しています。
企業が生産性向上のために設備投資を行うと、新商品やサービスの売上が拡大し、その利益の一部が人件費(賃上げ)に回されます。賃上げによって家計の可処分所得が増えると消費が拡大し、再び企業の投資余力が高まる -この好循環が「賃上げと投資が牽引する成長型経済」の核心です。
ケーススタディ(例):企業Aの好循環イメージモデル
- 企業Aは最新の製造設備を導入(投資)
- 生産性が20%向上し、売上が15%増加
- 売上の増加により、従業員の給与水準の引き上げ(ベースアップ)
- 社員の消費が増え、地元商店街の売り上げも好調に
- 地元商店街がA社の部品調達を拡大し、A社の事業規模がさらに拡大(再投資)
【用語解説】
- 実質賃金:物価変動を差し引いたうえで得られる購買力ベースの賃金
- 設備投資:企業が生産設備や技術開発に投じる資金
- 成長型経済:賃上げと投資が互いに作用し、持続的な経済成長を生み出す経済構造
高校生の皆さんはどう考えますか?
あなたが将来就職を考える企業を選ぶ際、どのような投資活動や賃上げ実績をチェックしますか?
中小企業支援とリスク
政府は「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」の一環として、5年間で約60兆円の生産性向上投資を官民で実現することを掲げています。全国約2,200か所の商工会・商工会議所や地域金融機関が、専門家派遣や伴走支援を通じて、設備更新やデジタル化などの省力化投資を多年度にわたりサポートします。
中小企業は、国内就業者の約7割を抱える日本経済の根幹ですが、人材育成や価格転嫁、事業承継・M&Aの支援が不十分だと、十分な賃上げやキャリア形成機会を確保できません。特に、中小企業336万社のうち約100万社の経営者が70歳以上である現状では、適切なM&Aや事業承継の仕組みがないと「黒字でも廃業」に追い込まれるリスクがあります。
ケーススタディ(例):企業Bのジレンマ
企業Bは創業50年の製造業。地域の支援を受けずに設備更新を先送りした結果、競合企業に対抗できず、人手不足も深刻化。賃上げ余地がなくなり、有能な若手社員は転職。結局、後継者問題も解決できず、市場からの撤退を余儀なくされました。
【用語解説】
- 生産性向上投資:生産設備やデジタル化への投資を通じて、単位労働当たりの付加価値を高める取組み
- 価格転嫁:コスト上昇分を適正に販売価格に反映させる(値上げの)仕組み
- 事業承継・M&A:経営者交代や企業統合を通じて、事業継続や成長を図る手法
高校生の皆さんはどう考えますか?
あなたが将来就職先を選ぶ際、この「賃上げ推進支援」の仕組みをどうチェックし、キャリア形成に活かせるでしょうか?
研究開発と輸出のエンジン
政府は「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」において、投資立国の実現の中核として、以下の“新たな勝ち筋”分野での研究開発・輸出を徹底的に後押しすると明記しています。
- ヘルスケア:予防・健康づくりや医療DX、バイオ技術など、国際市場を視野に入れた技術・サービス開発
- 防災:災害対策技術、インフラの強靭化に関わるソリューション
- 農林水産業:スマートアグリ・フードテックを駆使した高付加価値化
- コンテンツ産業:アニメ・ゲーム・デジタル・エンタメをはじめとするソフトパワーの輸出
- 観光・地域振興:デジタル技術で観光体験を高度化し、地方経済を支える新サービス
これらの分野には、官民合わせて2030年度には135兆円、2040年度には200兆円にのぼる研究開発助成や税制優遇、貿易・輸出支援策が集中投下される予定です。たとえば、2040年度の名目GDPは約1,000兆円を目指しています。(2024年の名目GDPは609兆円)
キャリア視点のポイント
- 研究職だけじゃない:企画・マーケティング、データ分析、製造管理、ロジスティクスなど、多様な職種で成長分野に参画可能。
- グローバル展開力:輸出支援を利用すれば、留学や語学力に不安があっても、国内拠点で海外市場を相手に働くチャンスが増大する。
- 地方創生×イノベーション:観光や農業分野では、地域発のスタートアップや事業承継型企業で、先進技術を用いて地域課題を解決する道も広がる。
政府支援メニュー例
| 分野 | 主な支援策 | 活用ポイント |
| ヘルスケア | 研究開発助成、医療DX補助、国際認証支援 | DXスキルがあれば研究開発以外にも参画可 |
| 防災 | インフラ実証プロジェクト、官民連携モデル事業 | 現場技術者・プロジェクト管理職の需要大 |
| 農林水産 | スマート農業補助、海外販路開拓支援 | 食×ITの融合分野で文系理系共に活躍可能 |
| コンテンツ | 海外展示会補助、著作権保護・契約法支援 | クリエイティブ職の国際競争力強化 |
| 観光 | デジタルツーリズム実証、地域振興プロジェクト補助 | 英語不要でITを使った仕組み構築も可能 |
このように、政府方針に合わせた研究開発・輸出支援を理解し、自分のキャリア構想と結びつけることは、将来の“勝ち筋”を自ら描けるヒントになります。
高校生の皆さんはどう考えますか?
あなたはどの分野で、自分の得意・好きなことを活かして「世界を相手に働く」チャンスを掴みたいと思いますか?
スタートアップ拡大と『貯蓄から投資へ』が生み出す新キャリア
政府は「スタートアップ育成5か年計画」において、今後5年間でスタートアップへの投資額を10倍に拡大し、人材・ネットワークの構築、資金供給の強化と多様な出口戦略、オープンイノベーション推進の3本柱で集中支援を行うと明記しています。
さらに、今回の強化策として「スタートアップ・エコシステムの構築」を掲げ、拠点都市の拡大やディープテック系や大学発ベンチャーの事業化支援を含む一気通貫の支援体制を強化するとされています。
「スタートアップは単なる新規創業ではなく、社会課題解決と新産業創出のエンジン。政府の後押しで、学生時代からの挑戦が新しいキャリア選択の軸になる」
キャリア視点のポイント
- “挑戦する文化”への参画機会:
ベンチャーインターンやビジネスコンテスト、大学発スタートアップ実習など、学内外で起業体験を積むプログラムが急拡大。 - 大企業との協業(コーポレートベンチャー):
オープンイノベーションを活用し、大企業のリソースを借りながら新規事業に携わる道も増加。 - リスクテイクと学び直し:
失敗から学ぶマインドセットや、複数の事業フェーズ(シード→シリーズA→…)を経験できるキャリアキャップストーンの意義。
政府のスタートアップ支援メニュー例
| 支援領域 | 主な施策例 | 活用イメージ |
| 人材・ネットワーク構築 | 起業塾プログラム、大学発ベンチャー創出支援 | 高校・大学と連携した起業体験プログラム、研究者と学生チームによる実践型プロジェクト |
| 資金供給の強化と出口戦略多様化 | 官民ファンドの出資枠拡大、成長を後押しするための税制面での優遇、スタートアップ向け保証制度 | 初期段階からの出資・融資、IPO前の大型ファイナンス準備 |
| オープンイノベーション | 大企業×スタートアップ連携プログラム、成長ステージに応じた投資、大学発の研究成果のマッチング支援 | 大手製造業の課題解決型長期インターンシップに学生チームが参加 |
高校生の皆さんはどう考えますか?
あなたがもし学生時代にスタートアップに関わるとしたら、どんな社会課題をビジネスで解決したいですか?また、その挑戦を支えるために、どの支援策を活用しますか?
家計における「貯蓄」から「投資」へ
政府は「資産運用立国」の実現を掲げ、高齢者を含めあらゆる世代がNISAの投資枠を活用し、計画的に資産運用を続けながらその成果を生活に活かせるよう制度の充実を図るとしています。
また、企業型DC(企業型確定拠出年金)やiDeCo(個人型確定拠出年金)の運用改善にも取り組み、全世代の安定的な資産形成を後押しする方針です。
- なぜ「投資」が必要か
- 物価上昇が続く中、銀行預金だけでは実質的な資産価値を守れない。
- 社会保障が縮小傾向にあるため、公的年金に頼るだけでは生活設計が不安定に。
- 政府が用意する主な手段
- つみたてNISA/一般NISA:非課税投資枠の拡大や対象商品の多様化を検討中。
- iDeCo:掛金の拠出・運用・受取すべてが税制優遇される個人年金制度の改善。
- 企業型DC:企業が従業員に対して丁寧な説明を行い、必要に応じて運用商品の見直しを行うことを促進。
ただし、これらの制度を活かし続けるには「十分な稼ぎ」が前提となります。生涯を通じて安定的に投資資金を捻出するためには、これまで示した政府の投資重点分野やスタートアップ支援など、政策の恩恵を受けやすい企業や業界を視野に入れておくことが重要です。
逆に、政府方針に対応できない組織に身を置くと、キャリア機会の損失だけでなく、家計の資産形成でも大きな機会損失を被る可能性があります。
高校生の皆さんはどう考えますか?
あなたがこれから働く業界や企業を選ぶ際、どのように「投資環境の整備状況」や「教育・研修制度」をチェックし、自分の資産形成戦略につなげられるでしょうか?
まとめ
政府が掲げる「貯蓄から投資へ」という方針は、私たち一人ひとりの人生設計やキャリア形成に直結する重要な社会ルールです。今後の社会は、賃上げや投資を継続的に実施できる企業や、新たな成長分野である研究開発・スタートアップ支援を積極的に活用する組織が大きな成功を手にします。逆に、これらの流れに乗れない企業や地域では、就業機会の減少や十分な収入を得られないというリスクが高まります。
金融教育やキャリア教育を担当する皆さんには、生徒たちが政府の戦略的な方向性を理解し、適切な企業選びや働き方の選択を行えるようサポートすることが求められています。政府の施策や支援制度をうまく活用する知識を伝えることで、生徒たち自身が、自らのキャリアを主体的に考え、資産形成の第一歩を踏み出すための基礎力を身につけることができるでしょう。
『貯蓄から投資へ』の流れは、将来のキャリア選択と密接に結びついています。
ぜひ、学校や教育現場での授業や指導に、本記事の内容を役立てていただければ幸いです。